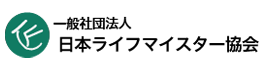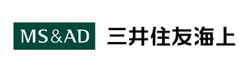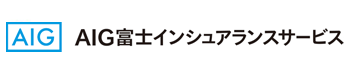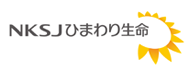【11/28(金) 無料体験会】「介護ストレス」と「脳の健康」から従業員を守る。issue+design × テオリア・テクノロジーズが共同開発した新セミナーを初開催|保険ニュース
【11/28(金) 無料体験会】「介護ストレス」と「脳の健康」から従業員を守る。issue+design × テオリア・テクノロジーズが共同開発した新セミナーを初開催
介護離職リスクへの対応と社員の脳の健康を支援し、人的資本経営時代の新たな両立支援のカタチを提案する人事・経営層向けセミナーを開発、提供開始。
[画像: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/20948/70/20948-70-13b82c513730816ef6f50913ca6aeb53-2574x1258.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
特定非営利活動法人イシュープラスデザイン(東京都文京区、代表:筧 裕介)は、テオリア・テクノロジーズ株式会社(東京都千代田区、代表取締役CEO:坂田 耕平)と協働で開発した、人事・経営層向け「認知症世界の歩き方 実践ワークショップ × 脳の健康セミナー」の無料体験会(11月28日開催)をお知らせします。
お申し込み: https://dementia1128.peatix.com/
本セミナーは、少子高齢化が進む日本で増加する「ビジネスケアラー」による「介護離職問題」と、雇用延長時代における社員の「脳の健康」維持・増進という二つの経営課題に対応することを目的とし、
科学的エビデンスと実践的なアプローチに基づいた解決策を提示します。
日本では40~50代を中心に、仕事と介護を両立する「ビジネスケアラー」が急増しています。
中でも大きな負担となるのが認知症の家族介護です。
突然の言動、理解できない行動、夜間の不穏や、コミュニケーションの断絶など。
これらは介護者に大きな心理的負荷をもたらし、生産性の低下、そして年間約10万人の介護離職につながっています。
「雇用延長時代」に不可欠な“脳の健康”リスク
定年延長・継続雇用が進む中、全従業員の認知機能や集中力・判断力の維持は、企業の生産性に直結する経営課題です。
加齢による認知機能低下リスク、判断力の低下や、脳疲労によるミス。そして生産性の落ち込みなど、
こうした“見えない脳のリスク”に対して、科学的視点からのアプローチは欠かせません。
2社で人事向けセミナーを実施する背景
これまでissue+designは「認知症世界の歩き方」プロジェクトを通じて認知症への理解促進と偏見解消に取り組み、テオリアは、東京都健康長寿医療センター監修のもと、「脳の健康」に関するエビデンスに基づいた情報提供やソリューション開発を行っています。
異なるアプローチで社会課題解決に取り組んできた両社が協働することで、企業が直面するこれらの課題に対し、具体的な解決策と、持続可能な組織を築くための新たな視点を提供することを目的としています。
認知症の方の行動の背景を体験的に理解し、適切な対応策を発想できるようになります。ロジカルな背景を知ることで不安が和らぎ、「工夫次第で共に暮らせる」感覚に変わったという検証結果も得られています。
認知症の方の行動を「問題」ではなく「現象」として理解し、介護自体の負荷を下げるコミュニケーションと暮らしのデザインを学べます。
2. 社員の生産性と持続性の向上(脳の健康):
将来の認知機能低下リスクだけでなく、現在の仕事のパフォーマンス維持・向上に直結する脳の健康法を学べます。
東京都健康長寿医療センター副院長 岩田 淳先生監修のもと、エビデンスに裏付けられた「明日から始められる行動変容」を具体的に解説し、社員一人ひとりのセルフマネジメントを促します。
3. 高い意識変容の実績:
このセミナーの開発にあたって行った企業向けの検証では、合計600名以上の方にご参加いただき、90%以上の方が満足し、意識が変わったと回答しました。特に、93.9%の参加者が「認知症は自分にも関係がある」と感じ、83.4%の方が認知症の方への印象が「変わった」と答えています。
・従業員の介護負荷を具体的に軽減し、心理的安全性を高めたい人事・健康経営推進担当者様。
・雇用延長を見据え、従業員自身の脳の健康と未来のパフォーマンス維持を支援したい企業様。
(特に、ベテラン層のナレッジ維持・活用、全従業員の集中力・判断力向上を課題としている企業様)
・制度だけでなく、実際に従業員が「使える」「役立つ」実践的な教育施策を探しているご担当者様。
【人事戦略の必須課題】デザインと科学で解き明かす
従業員の「介護ストレス」と「脳の健康」対策セミナー
<概要>
日時: 2025年11月28日(金)16:00~17:00
形式:オンライン(Zoom)
参加費: 無料
対象:企業経営者様、人事部門・総務部門のご担当者様、健康経営推進のご担当者様
お申し込み: https://dementia1128.peatix.com/
主催:issue+design、テオリア・テクノロジーズ
共催:株式会社インターネットインフィニティ
セミナー体験会のハイライト
この共同セミナーは、単なる制度紹介や学術的な見解で終わらせません。
科学的なエビデンスに基づき、明日から行動を変容させる具体的な知識と、介護負荷をリアルに下げるための具体的なコミュニケーション・デザイン手法を学べます。
~「理解できない行動」の理由が分かり、介護の負荷が激減する~
大人気書籍『認知症世界の歩き方』をベースに、認知症ご本人から「見える世界」「体験していること」を追体験します。 * 問題行動の原因推察: なぜそうした行動を取るのか?その背景にある本人の世界を動画などで疑似体験し、認知症の方の行動を「問題」ではなく「現象」として理解します。コミュニケーションと暮らしのデザイン: 原因を理解することで、どう声をかけるか、どう生活環境をデザインするかといった、介護自体の負荷を下げる実践的なアプローチを学びます。
【第2部】 テオリア・テクノロジーズ:パフォーマンスを維持する『脳の健康セミナー』(体験):20分
~東京都健康長寿医療センター監修。エビデンスに基づいた脳の健康セルフマネジメント~
将来の認知機能低下リスクに備えるだけでなく、現在の仕事のパフォーマンス維持・向上に直結する脳の健康法を、国内外の研究理解に熟知した専門家が解説します。 脳と認知機能の関係理解: 日常生活や仕事の負荷が脳に与える影響、そして認知機能との関係を理解します。エビデンスベースの行動変容: 「何をすればいいか?」に明確に答え、エビデンスに基づいて日々できることを具体的に提示。従業員一人ひとりが明日から始められるセルフマネジメントを促します。
【フォローアップ】 インターネットインフィニティ:従業員向け介護と仕事の両立支援について:10分
~介護コンシェルジュサービスについて~なぜ今、この共同セミナーが必要なのか? 90%以上の満足度と意識変容を達成!
前回企業向けに実施した検証には600名以上が参加し、非常に高い評価を得ました。詳細はこちら。「介護の理解」と「脳の健康」を両面からサポートすることで、介護離職の予防、生産性の低下防止、従業員の心身の健康維持、そして企業へのエンゲージメント向上に貢献します。特に従業員の脳の健康維持は、人的資本経営を推進する上での具体的な投資となります。
認知症ケアデザインの issue+designと、東京都健康長寿医療センターの岩田先生に監修いただいた科学的知見を持つテオリア・テクノロジーズがタッグを組み、実践的かつ信頼性の高いプログラムを提供します。
多くの皆様のお申し込みを心よりお待ちしております。
詳細・お申し込みはこちら
■テオリア・テクノロジーズ株式会社について
テオリア・テクノロジーズは「認知症との向き合い方を、テクノロジーで変えていく。」をミッションに掲げ、エーザイグループの一員として認知症という社会課題の解決を目指しています。
認知症の当事者やご家族、医療関係者との対話から得た膨大な知見とAIなどのテクノロジーを掛け合わせ、健常・未病時の備えから診断後のケアまで、一貫して認知症に関する事業に取り組んでいます。
<会社概要>
本社所在地:東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 17F
代表者:坂田 耕平
設立:2023年9月4日
資本金:8億円
事業内容:医療・健康に関するデータを活用したサービス、その他ヘルスケア関連サービスの提供
URL:https://theoriatec.com/
■issue+designについて
「社会の課題に、市民の創造力を。」を合言葉に、2008年から始まったソーシャルデザインプロジェクト。市民・行政・企業が参加し、地域・日本・世界が抱える社会課題に対して、デザインの持つ美と共感の力で挑む。東日本大震災のボランティアを支援する「できますゼッケン」、妊娠・出産・育児を支える「親子健康手帳」、人との出会いを楽しむ旅のガイドブック「Community Travel Guide」、300人の住民とともに地域の未来を描く「高知県佐川町 みんなでつくる総合計画」認知症の方が生きる世界を見える化する「認知症世界の歩き方」他、行政や企業とともに多様なアプローチで地域が抱える課題解決に挑むデザインプロジェクトを多数実施中。
URL:https://issueplusdesign.jp/
プレスリリース提供:PR TIMES
[画像: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/20948/70/20948-70-13b82c513730816ef6f50913ca6aeb53-2574x1258.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
特定非営利活動法人イシュープラスデザイン(東京都文京区、代表:筧 裕介)は、テオリア・テクノロジーズ株式会社(東京都千代田区、代表取締役CEO:坂田 耕平)と協働で開発した、人事・経営層向け「認知症世界の歩き方 実践ワークショップ × 脳の健康セミナー」の無料体験会(11月28日開催)をお知らせします。
お申し込み: https://dementia1128.peatix.com/
本セミナーは、少子高齢化が進む日本で増加する「ビジネスケアラー」による「介護離職問題」と、雇用延長時代における社員の「脳の健康」維持・増進という二つの経営課題に対応することを目的とし、
科学的エビデンスと実践的なアプローチに基づいた解決策を提示します。
■背景
増え続ける「ビジネスケアラー」、深刻化する介護ストレス日本では40~50代を中心に、仕事と介護を両立する「ビジネスケアラー」が急増しています。
中でも大きな負担となるのが認知症の家族介護です。
突然の言動、理解できない行動、夜間の不穏や、コミュニケーションの断絶など。
これらは介護者に大きな心理的負荷をもたらし、生産性の低下、そして年間約10万人の介護離職につながっています。
「雇用延長時代」に不可欠な“脳の健康”リスク
定年延長・継続雇用が進む中、全従業員の認知機能や集中力・判断力の維持は、企業の生産性に直結する経営課題です。
加齢による認知機能低下リスク、判断力の低下や、脳疲労によるミス。そして生産性の落ち込みなど、
こうした“見えない脳のリスク”に対して、科学的視点からのアプローチは欠かせません。
2社で人事向けセミナーを実施する背景
これまでissue+designは「認知症世界の歩き方」プロジェクトを通じて認知症への理解促進と偏見解消に取り組み、テオリアは、東京都健康長寿医療センター監修のもと、「脳の健康」に関するエビデンスに基づいた情報提供やソリューション開発を行っています。
異なるアプローチで社会課題解決に取り組んできた両社が協働することで、企業が直面するこれらの課題に対し、具体的な解決策と、持続可能な組織を築くための新たな視点を提供することを目的としています。
■提供する価値
1. 介護離職リスクの低減と介護負荷の軽減:認知症の方の行動の背景を体験的に理解し、適切な対応策を発想できるようになります。ロジカルな背景を知ることで不安が和らぎ、「工夫次第で共に暮らせる」感覚に変わったという検証結果も得られています。
認知症の方の行動を「問題」ではなく「現象」として理解し、介護自体の負荷を下げるコミュニケーションと暮らしのデザインを学べます。
2. 社員の生産性と持続性の向上(脳の健康):
将来の認知機能低下リスクだけでなく、現在の仕事のパフォーマンス維持・向上に直結する脳の健康法を学べます。
東京都健康長寿医療センター副院長 岩田 淳先生監修のもと、エビデンスに裏付けられた「明日から始められる行動変容」を具体的に解説し、社員一人ひとりのセルフマネジメントを促します。
3. 高い意識変容の実績:
このセミナーの開発にあたって行った企業向けの検証では、合計600名以上の方にご参加いただき、90%以上の方が満足し、意識が変わったと回答しました。特に、93.9%の参加者が「認知症は自分にも関係がある」と感じ、83.4%の方が認知症の方への印象が「変わった」と答えています。
■このような企業様におすすめです
・介護離職を防止し、大切な人材の流出を防ぎたい経営層・人事担当者様。・従業員の介護負荷を具体的に軽減し、心理的安全性を高めたい人事・健康経営推進担当者様。
・雇用延長を見据え、従業員自身の脳の健康と未来のパフォーマンス維持を支援したい企業様。
(特に、ベテラン層のナレッジ維持・活用、全従業員の集中力・判断力向上を課題としている企業様)
・制度だけでなく、実際に従業員が「使える」「役立つ」実践的な教育施策を探しているご担当者様。
■11/28 無料体験会のご案内
企業経営者および人事担当者の皆様に、社員の両立支援の新たなヒントと、人的資本の価値最大化に向けた具体的な戦略を見つけていただく機会を以下の内容で開催します。【人事戦略の必須課題】デザインと科学で解き明かす
従業員の「介護ストレス」と「脳の健康」対策セミナー
<概要>
日時: 2025年11月28日(金)16:00~17:00
形式:オンライン(Zoom)
参加費: 無料
対象:企業経営者様、人事部門・総務部門のご担当者様、健康経営推進のご担当者様
お申し込み: https://dementia1128.peatix.com/
主催:issue+design、テオリア・テクノロジーズ
共催:株式会社インターネットインフィニティ
セミナー体験会のハイライト
この共同セミナーは、単なる制度紹介や学術的な見解で終わらせません。
科学的なエビデンスに基づき、明日から行動を変容させる具体的な知識と、介護負荷をリアルに下げるための具体的なコミュニケーション・デザイン手法を学べます。
■体験会プログラムの内容
【第1部】 issue+design:介護負荷を下げる『認知症世界の歩き方セミナー』(体験):20分~「理解できない行動」の理由が分かり、介護の負荷が激減する~
大人気書籍『認知症世界の歩き方』をベースに、認知症ご本人から「見える世界」「体験していること」を追体験します。 * 問題行動の原因推察: なぜそうした行動を取るのか?その背景にある本人の世界を動画などで疑似体験し、認知症の方の行動を「問題」ではなく「現象」として理解します。コミュニケーションと暮らしのデザイン: 原因を理解することで、どう声をかけるか、どう生活環境をデザインするかといった、介護自体の負荷を下げる実践的なアプローチを学びます。
【第2部】 テオリア・テクノロジーズ:パフォーマンスを維持する『脳の健康セミナー』(体験):20分
~東京都健康長寿医療センター監修。エビデンスに基づいた脳の健康セルフマネジメント~
将来の認知機能低下リスクに備えるだけでなく、現在の仕事のパフォーマンス維持・向上に直結する脳の健康法を、国内外の研究理解に熟知した専門家が解説します。 脳と認知機能の関係理解: 日常生活や仕事の負荷が脳に与える影響、そして認知機能との関係を理解します。エビデンスベースの行動変容: 「何をすればいいか?」に明確に答え、エビデンスに基づいて日々できることを具体的に提示。従業員一人ひとりが明日から始められるセルフマネジメントを促します。
【フォローアップ】 インターネットインフィニティ:従業員向け介護と仕事の両立支援について:10分
~介護コンシェルジュサービスについて~なぜ今、この共同セミナーが必要なのか? 90%以上の満足度と意識変容を達成!
前回企業向けに実施した検証には600名以上が参加し、非常に高い評価を得ました。詳細はこちら。「介護の理解」と「脳の健康」を両面からサポートすることで、介護離職の予防、生産性の低下防止、従業員の心身の健康維持、そして企業へのエンゲージメント向上に貢献します。特に従業員の脳の健康維持は、人的資本経営を推進する上での具体的な投資となります。
認知症ケアデザインの issue+designと、東京都健康長寿医療センターの岩田先生に監修いただいた科学的知見を持つテオリア・テクノロジーズがタッグを組み、実践的かつ信頼性の高いプログラムを提供します。
多くの皆様のお申し込みを心よりお待ちしております。
詳細・お申し込みはこちら
■テオリア・テクノロジーズ株式会社について
テオリア・テクノロジーズは「認知症との向き合い方を、テクノロジーで変えていく。」をミッションに掲げ、エーザイグループの一員として認知症という社会課題の解決を目指しています。
認知症の当事者やご家族、医療関係者との対話から得た膨大な知見とAIなどのテクノロジーを掛け合わせ、健常・未病時の備えから診断後のケアまで、一貫して認知症に関する事業に取り組んでいます。
<会社概要>
本社所在地:東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 17F
代表者:坂田 耕平
設立:2023年9月4日
資本金:8億円
事業内容:医療・健康に関するデータを活用したサービス、その他ヘルスケア関連サービスの提供
URL:https://theoriatec.com/
■issue+designについて
「社会の課題に、市民の創造力を。」を合言葉に、2008年から始まったソーシャルデザインプロジェクト。市民・行政・企業が参加し、地域・日本・世界が抱える社会課題に対して、デザインの持つ美と共感の力で挑む。東日本大震災のボランティアを支援する「できますゼッケン」、妊娠・出産・育児を支える「親子健康手帳」、人との出会いを楽しむ旅のガイドブック「Community Travel Guide」、300人の住民とともに地域の未来を描く「高知県佐川町 みんなでつくる総合計画」認知症の方が生きる世界を見える化する「認知症世界の歩き方」他、行政や企業とともに多様なアプローチで地域が抱える課題解決に挑むデザインプロジェクトを多数実施中。
URL:https://issueplusdesign.jp/
プレスリリース提供:PR TIMES
記事提供: PR TIMES
- 【ペット保険人気ランキング】2025年11月最新版を発表!|ペ... 2025年11月18日更新
- 「【人事戦略の必須課題】デザインと科学で解き明かす 従業員... 2025年11月18日更新
- 新商品「チケット保険」の販売決定について~エンタメに安心... 2025年11月18日更新
- 台湾ケアテック連盟、高齢者向けスマート介護製品で日本の高... 2025年11月18日更新
- 【ascure Dr. 高血圧治療】健康経営銘柄・ホワイト500を中心... 2025年11月18日更新
人気記事ランキング
- 重粒子線がん治療 2011年08月24日
- 共同募集と代理店分担 2017年01月12日
- 不整脈と告知するなかれ! 2013年09月07日
- 初代ソニープルデンシャ... 2011年11月25日
- 全国で年商300億円以... 2014年10月21日
保険
![保険相談・保険見直し[とれまが保険] 保険相談・保険見直し[とれまが保険] - 保険の総合情報ポータルサイト](https://www.toremaga.com/images/hoken/common/logo_toremaga2.gif)